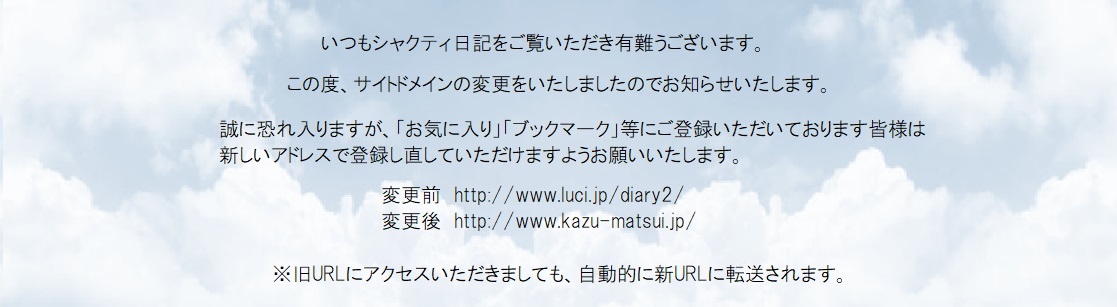愛されることへの飢餓感
養護施設光りの子どもの家の菅原哲男先生の書いた本「誰がこの子を受けとめるのか: 光の子どもの家の記録」
(虐待を被けた子どもは、いつか大人になって自分の子どもを虐待する親になる!―そんな常識化した負の連鎖を乗り越えるために。子どもを受けとめる「家族の力量」「社会的養育の力量」がいま問われている。家族の愛に等しい養護をめざした「光の子どもの家」十九年の記録。)
を、もう一度、読み返しています。
いま、政府が「保育の受け皿」「雇用労働施策」という言葉を使って、(女性が輝く、という言葉も使って)もう50万人0、1、2歳児を親から引き離そうとしている時に、もう一度読まれなければいけない、現場からの貴重な証言だと思います。この国が成り立つために、乳幼児期の人間関係(特に親子関係)に、何が求められているのか、
菅原さんは書くのです。
「職員が旅行に行ったら担当している子どもにしかお土産を買わない、そうでなければならない」
「みんなと一緒、を子どもたちは極端に嫌う」。
(平等の対極に親子がある。そうだろうな、と思います。:松居)
「『仕事で子どもを愛せるか』これは光りの子どもの家の当初からの課題である。」
「養育に最も欠けてはならないエッセンスは労働とは次元の違う無償の行為なのである。」
(ここから松居です。)
児童養護施設で過ごす人間たちの時間が、社会に向かってそう叫んでいます。『仕事で子どもを愛せるか』。政府が閣議決定で「保育は成長産業」と位置付けたいま、「保育界」が思い出さなければいけないエッセンスだと思います。労働にはちがいない。しかし、そうした経済的な仕組みが作られる以前の、もっと古いきまりが「子育て」のエッセンスとしてあった。その次元の人間のつながりが欠けてくると、人間社会は成り立たない。だから保育士は子どもたちを愛さなければならない。
菅原さんは書きます。
「何よりも愛されることへの飢餓感、ある者は不感を疑わせるほどに愛を知らないできてしまった時間の長さに、関わりの手がかりさえ見当たらない」
菅原さんが受け止めようとしている子どもたちの「愛されることへの飢餓感」は、確かに普通(尋常)ではないかもしれない。でも、私が中学校へ講演に行き、肌で感じる子どもたちの幼さも、その延長線上にあるのだと思うのです。この本を読んでいると乳幼児期の愛着関係がいかに決定的かが見えてきて、いまの政府の施策が恐ろしくなる。道徳教育なんて浅い次元の問題ではない。愛されることへの飢餓感、それがいじめや不登校、少年犯罪や理解できない犯罪の根底にあるような気がします。
菅原さんがあとがきに書きます。
「この本では、親の愛に溢れる最初の『受けとめ』がなければ、子どもは育つことができないこと、母親(またはそれに代わりうる人)の『受けとめる愛』を失った幼児たちは心も体も『凍りついている』ことを切実に訴えています。
『光の子どもの家』の幼児たちが学童期を迎え、青春前期を経て大人になるあいだに、どんな苦しみと哀しみの経験を超えて『生きる力』を身につけ、社会へと旅立つことができるようになったのか。その記録は同時に、今を生きるすべての子どもたち、これから生まれてくる子どもたちに何が必要なのかを伝える大切な参照の経験になっています。」
菅原さんがこれを書いたのが二十年前(本になったのは十三年前)。これほどの証言が児童養護施設という、子育てにおける最後の砦から発せられているのに、なぜ政府は幼児と親の関係を「負担」とみなしたり、「社会進出」を妨げる「壁」と言ったりするのか。現在の子ども・子育て支援新制度の元になる「新システム」が形づくられた時、それを進めた厚生労働大臣が「子育ては専門家に任せておけばいいのよ」と言った。そして、もうその頃から、中学の先生が「私たちは保育をしている」と私に言い、園長が「保育園は仮養護施設状態に追い込まれている」と言っていた。
このままでは学校がもたない。保育園ももたない。共倒れになってゆく図式はすでに見えているのに、「待機児童をなくせ」というかけ声だけが選挙の度に響く。0、1、2歳児は保育園の前で「ここに入りたい」と言って待機はしていない。それを思い出さない限り、仕組みの崩壊は止まらない。

荒れる児童
以前、新聞に、文科省の小学生の問題行動調査についての記事が出ました。「反抗、暴言、荒れる児童」(社会のひずみ、ストレスに)という題名(毎日新聞)。「小学校教諭からは悲鳴が上がり、専門家は『荒れの背景には貧困など社会のひずみが子どものストレスになって表面化している』と指摘」とありました。
いま、入学前の子どもにストレスとなっている「社会のひずみ」は、貧困が直接的な原因ではなく、財政・人材不足の中で拡張と質の低下を余儀なくされた保育現場と、「子どもは誰かが育ててくれるもの」という意識で園長や役場の職員に無理な要求する、第一義的責任という常識を失った親たちの増加だと思います。親として育ち切っていない親の増加が、集団保育や教育を介して全ての子どもたちのストレスになってきている。貧困は、そうしたストレス社会が生む副産物と捉えるほうが正しいのではないか。
発展途上にある未だ保育制度が整っていない貧しい国々の小学生は暴言を吐かないし、それほど荒れてもいない。家庭における愛着関係がしっかりしていれば、子どもはそんなに荒れない。
義務教育が整って間もない発展途上国の学校が秩序正しく安定しているのを見れば、先進国が直面している「社会のひずみ」は、貧富の差とは別の次元の、親子の愛着関係、社会における信頼関係の不足が原因であって、それによる子どもたちの不安感が学校における「荒れ」を引き起こしていることがよくわかります。子どもたちが、精神的な安定、そして行き場を失い、荒れている。

未成年者による、人間性を問いたくなるような事件が起ります。
労働力を増やすために政府がもう40万人三歳未満児たちを保育施設で預かれ、と数値目標を立て、「親と居たい、誰かを独占したい」という、喋れない、主張できない弱者の願いを無視する政策をとり続ければ、こうした問題を起こす予備軍は増え続け、責任の目を向けられる教育現場が追い込まれていく。
愛着関係が希薄だった子どもたちの寂しさや悪意に対する反応はすばやい。肌が繊細に、敏感になっているから、なおいっそう愛情を養分にしようとしてもがく。だから学校に入って、教師たちの視線の温度差がより決定的になってしまうのです。そして、その要望と視線に、教師たちの決意が追いつかない。
気づいてほしい。三歳までの子どもたちの日々の過ごし方が、この国の未来を決める、ということに。
厚労省が出した保育所保育指針解説書というのがあって、その最後にこう書いてあるのです。
「保育所は、人が『育ち』『育てる』という人類普遍の価値を共有し、継承し、 広げることを通じて、社会に貢献していく重要な場なのです。」
そのとおり!
そうであってほしいと思いますし、そうでなければ人類が危うい。そして、幼児たちを眺めながら、人類普遍の価値を人間に教えてくれるのが彼等なのだということに、再び、気づかなければいけません。